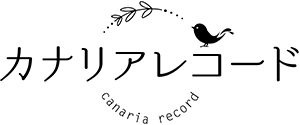「絡めとられた心」 文:田中バター
バタン、と勢いよく自室の扉が閉まると、私はそのままずるずるフローリングの床に座り込んだ。
我慢できず溢れ出した涙が抱えた膝をジワリと濡らしていく。
浮気したことをあんな風に開き直るなんて信じられない。
今度こそ、とそう思っていた。
もしかしたら私の言葉を思い出して浮気をやめてくれるんじゃないか、なんて。
「……ほんと、バカみたい」
ぼそりとつぶやいた言葉は、自分でも驚くほど掠れていて、思いのほか自分が傷ついていたのだということに嫌でも気づかされる。
いつの間に私たちの関係は変わってしまったんだろう。
昔はもっと普通の恋人同士だったはずなのに……。
確かにいい加減なところはあったけれど、バレーに対しては純粋に向き合っていたし、こんなにも自分本位で女にだらしない性格じゃなかった。
いつの頃か、周りがめきめきと頭角を現した大吾の実力に気づき、もてはやし始めてから大吾の中で何かが変わってしまった気がする。
『あんな男のどこが好きなの?』
大吾と付き合うようになってから、そう聞かれたことなんて両手では足りないほどにある。
私だって、何度別れようと思ったかわからない。
でも『どこが』と聞かれたら大吾の好きなところは胸を張って言える。
私は、バレーをしているあいつがどうしようもなく好きなのだ。
どんなに怒っていても、泣けるほど雑な扱いをされても、大吾がバレーをしている姿を見たらそんな気持ちはどこかに行ってしまう。
誰よりも高く、力強く飛ぶ大吾は、ひいき目なしにしてもかっこいいと思うし、しなやかに引き締まった身体が弓なりに反られ、瞬きも許されないスピードでボールを打ち込む姿を見て惚れるなという方が無理な話だ。
そう真剣な目で友人に話すと、大抵『あんたって趣味悪いよね』と言われる。
普段の大吾を知っていればそう言うのは当たり前だろうし否定も出来ない。
まぁ、そんな風に人の趣味をせせら笑っていた友人がその翌週にはあいつと浮気していた時はこちらがあきれて笑ってしまったけれど。
大吾はファンの女はもちろん、私の友達だって構わず誘われれば簡単に寝る。
でも、最終的に私のところに戻ってきてくれるなら構わない。
――初めはそんな風に思える余裕があった。
今思えば、そう思い込まないと自分を保てなかったんだろう。
それを私にわからせたのは、直接ではないにしろ彼の浮気現場を目撃してしまった時だった。
電話口から聞こえる、明らかに情事の最中を思わせる乱れた吐息や、後ろにうっすらと聞こえる衣擦れとベッドの音。
少しだけかすれた声が、私に向けるものと同じだと気づいた瞬間、私の中で必死に保っていたものが一瞬にして崩れ去ってしまった。
本当に私が一番だっていう確信はある?
もし今抱いている女が本命で、私の方が浮気相手だったら?
今までの私の言葉なんかただの戯言じゃないか。
そう考えたら今まで自分が自慢げに立っていた場所が、とたんに砂で出来た城に思えてきた。
考えてみたら、最近は大吾と会ったところでやることはいつもセックスばかりだった。
私から呼び出すときはまだしも、あいつから呼び出された時にはすぐさまベッドへ直行する。
会うなり唇を塞がれ、彼の望むままに奉仕をし、彼を気持ちよくすることで自分の快楽へとすり替えるのはいつものことだ。
最初は少し不満だったけれど、それでも喜びに変えることが出来たのは、私の手管が育つにつれ顕著に反応を示す彼が可愛らしく思えてきたからだ。
大きく舐め上げる度にかすかに漏れる、いつもより上擦って掠れた声がセクシーだったり、頭に置かれた指が髪を撫でるように震えるのが嬉しかったり、好きなところを挙げていけば切りがない。
快楽に素直な彼は、気持ち良ければ気持ちいいというし、上手くなれば褒めてもくれる。
ただ、それが気まぐれすぎていつやってくるかはわからないというだけで。
そのほんの少しのご褒美欲しさに呼ばれればついて行ってしまうのだから、自分でもバカだなぁとは思っている。
もう一緒にいるのは限界かもしれないという考えはずっと頭の中にあった。
それでも、あと一度だけ、と縋る様に自分を誤魔化して彼に何度目かのお願いする。
「もう絶対に浮気しないで」
そう泣いて縋り付く私に、いつものように大吾はおざなりに頷いていた。
頷いて、いとも簡単に約束を破るのだ。
そして見事に今日、無残に打ち砕かれた私の心は、それでもあいつを求めて離れたくないのだと血を流しながら訴えかけてくる。
――彼が私だけで満足できるようなものは何かないか?
「お前で満足出来りゃわざわざ他の女のとこなんか行かないんじゃねえか?
ま、出来ればの話だけど」
そう面白半分に告げられた彼の言葉を頼りに、必死に何かないか考える私がいる。
大吾をつなぎとめておけるものならなんだってやってやる。
たとえそれが本来望んでいた形ではなくても、他の女に取られるよりはよっぽどましに思えてくる。
彼に何度も砕かれ、それでも必死につなぎとめていた心は、どうやらだいぶ歪につなぎ合わさってしまったみたいだ。
彼との関係を変えるためにあがく私へ光明が射すきっかけになったの一冊の本だった。
どこにでもある、女性向けのちょっとエッチな特集記事。
そこに書かれていたことは眉唾物だったけど、その時の私にはなぜか『これしかない』と、そう思えてしまった。
さすがに好奇心旺盛な大吾とはいえ、知識としてはあっても試したことはないだろう。
そう考えだしたら行動するのは早かった。
雑誌で得た知識を広げて、道具もそろえてみる。
いきなりの実戦では自信がなくて、一度恐々自分で試してもみた。
身体の作りの違いからか本に載っていたようにはうまくいかなかったけれど、手順がわかったからそれで良しとする。
どういう方法でなら彼の興味を引けるかも、無い知恵を絞って考えた。
あとは彼が私から離れていけないよう上手く誘導するのみだ。
一世一代の大勝負。
大げさかもしれないけれど、私の中ではそのくらいの覚悟を持った賭けだ。
私が少しでもミスをしたらすべてが水の泡。
そう思うと怖かったけれど、そもそもここで行動を起こさなかったら遅からず離れて行ってしまうだろう未来を思えば不思議と落ち着いてくる。
彼を手放したくない。
たったそれだけの想いが、これからきっと、私を、彼を狂わせていくんだろう。
分かっていてももう止められない。
「――ねぇ、前立腺マッサージって知ってる?」
震える手を誤魔化すように、私は雑誌を持つ指にぎゅっと力を込めた。
END